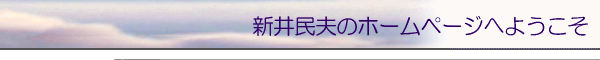

研究は社会のために役立つことが必要です.それが今すぐである必要はなくても,10年先,100年先にもこのような研究をした先人が居たのだと再認識されるような仕事をしたく思います.
このHome Pageでは,研究内容をできるだけ多角的に表現しようと心がけました.時代と共に変化していった研究の目的を顧みる余裕を持ちたいからです.
研究部門全体の研究の現状 昨年度今年度の研究室での研究の現状を説明します
- 主要論文 代表的な研究を示します.
- 研究の歴史 時代と共に変化してきた研究を概観します
- 研究の現状 昨年度今年度の研究室での研究の現状を説明します
- 年度別論文リスト 年度毎に新井研のすべての論文・発表のリストです.
- 分野別論文リスト まだ準備できていませんが,分野毎の成果を示します.
 |
主要論文 主要論文として,10編とその内容を簡単に示す.
- 新井民夫:組立成功率,精密機械,Vol.No.PP.−
組立....
- 著者:題名,掲載誌,Vol.No.PP.−
研究の歴史 時代と共に変化してきた研究を概観します
大学を卒業してからの研究内容について,年代順に説明しよう.
- 自動組立: 1970年に精密機械工学科を卒業.卒論の指導教官は山口隆男教授で,「人工義手の研究」を行った.山口先生はこの歳で定年であったので,大学院は佐田・木下研に入り,組立の研究に着手.
丸棒丸穴の挿入作業を研究した.
- 幾何推論: 1979年8月〜1981年8月の2ヵ年,英国Edinburgh大学人工知能科(Dept. of Artificial Intelligence)のRobin Popplestone 先生の下に留学した.英国British Councilの2ヵ年のFellowshipをとっての留学である.ここで,ロボットのプログラミングの研究を行った.内容的には幾何推論であった.
- ロボット言語: 英国から帰国すると,ちょうど,ロボット言語の調査研究が日本産業用ロボット工業会にて進められていた.佐田登志夫教授の下でロボット言語の提案をし,かつ,松元明弘(当時助手)君と共に開発をした.
- クレーンとロボット:マニピュレータの研究は段々難しくなり,そこで,重量物の組立に取り組んだ.その典型的な研究がクレーンとロボットとの協調制御であった.重量物になるとそれを支えているロボットと柔らかいロボットとみなせる.そこで,複数のばね系による重量物の制御問題となった.
- 複数移動ロボット: 柔らかいロボットの協調制御は,幾何学的干渉をばねで力学的干渉に変換して制御することとなる.同じことが移動ロボットでも成立する.移動ロボットの場合には,ノンホロノミックな特性が制御上の拘束条件になるので,全方向移動ロボットで椅子の搬送,大型物の搬送を研究した.
- 距離画像: ロボットのVisionの導入で悩んでいるときに,キャノンから距離センサーを借り受けて,距離画像の研究を始めた.
- MMHS: IMSの国際共同研究のひとつ.Metamorphic Material Handling Systems. 鹿島や間組,早稲田大学と共におこなった.我々は,移動ロボットを連結して,仮想的なベルトコンベアを構築する実験で,「変態可能な」システムを構築した.
- HMS: IMSの国際共同研究のひとつ.Holonic Manufacturing Sytems. 日立,東芝,Fanuc, 安川電機,大隈,慶応,神戸大,大阪府立大,などと一緒に自律分散生産システムを開発した.成果は学術論文として発表し,かつ,デモも行ったが,それ以外に,縦書きの本にして出版した.
- 巧みな操作: 元々,組立動作を研究していたこともあり,モノを運ぶ,動かすことには興味があった.そこで,Graspless Manipulationの研究が,組立研究とBehavior研究と幾何推論のちょうど中間に存在するの始めた.
- 環境設計: Social Robot Projectを進めていたとき,ロボットの知能の発達は極めて遅いと嘆かざるを得なかった.そこで,環境側に知能を埋め込むかあるいは環境側の設計をすることを提案し,Landmarkの研究を行った.
- 技能の抽出: マニピュレーションも協調も上手な動かし方である.これを技能と呼ぶ.人間は技能をうまく使って,ロボットを動かす(ロボットのプログラムをする).そこで,技能を抽出してそれらを連結することを研究している.
- 人間共存系: 人間とロボットとが共存するには何が必要なのか?マンマシーンインターフェースの研究や知情意の検出の研究もされているが,何が協調の関係なのかを探る研究を始めている.
- サービス工学: ここ3年間は新しい工学としてサービス工学を提唱している.その内容は別ページにしめそう.
研究の現状 昨年度今年度の研究室での研究の現状を説明します
年度別論文リスト 年度毎に新井研のすべての論文・発表のリストです.
分野別論文リスト まだ準備できていませんが,分野毎の成果を示します.
| 研究業績についてのページでした. |