学生参加者のプロセス
学生参加者のプロセス
ディスカッションと発表会は学生主体のイベントですし,なんといっても夏の「学校」ですから,以下の説明をよく読んで積極的に取り組んでください.
(1) [事前学習]割り当て必読資料の精読
【重要】前もって割り当て必読資料を必ず読み,レジュメを作成してきてください.
1. 参加者名簿で自分が属するグループつまり1日目の輪講の番号を確認します.
2. Webサイトから1日目の輪講の必読資料と参考文献をダウンロードします.
左欄の「輪講資料」という項目を選び,該当論文をクリックします.
(IDとパスワードは,参加登録された方にメールにて連絡済みです.)
左欄の「輪講資料」という項目を選び,該当論文をクリックします.
(IDとパスワードは,参加登録された方にメールにて連絡済みです.)
3. 必読資料に対して内容を簡潔にまとめ,論文紹介用のレジュメを作成します.
(ディスカッションで内容を紹介しますので,8部ほどご用意ください.)
(ディスカッションで内容を紹介しますので,8部ほどご用意ください.)
4. 読んだ論文に基づいて,自分なりに研究の展開を考えます.
(時間があれば参考文献や2日目の輪講の資料も読んでください.)
(時間があれば参考文献や2日目の輪講の資料も読んでください.)
(2) [1日目夜]グループディスカッションA
5つのグループに分かれて,各講師を(いる場合はモデレータも)囲んで,5室パラレルで行います.
0. グループを,【学生3名程度】+【一般3名程度】の2つのサブグループに分けます.
1. サブグループ単位で読んだ必読資料の内容を紹介します【20分程度】.
2. サブグループのまま,【必読資料】に基づいて疑問点や展開(例えば「こんな研究テーマを設定すると面白いのでは?」)について議論します【30分程度】.
この際,学生1名が【記録係】となって議事録をとります.
この際,学生1名が【記録係】となって議事録をとります.
3. 各サブグループから議論の結果を報告してもらい,出てきたアイデアをグループ全員で共有します【10分程度】.
4. 講師やモデレータの方から寸評をもらいつつ,各アイデアについてグループ全員でディスカッションします【30分程度】.
※必ずしもアイデアを一本化する必要はなく,自由にディスカッションして,3日目の発表会のための材料を見出す作業と位置づけます.
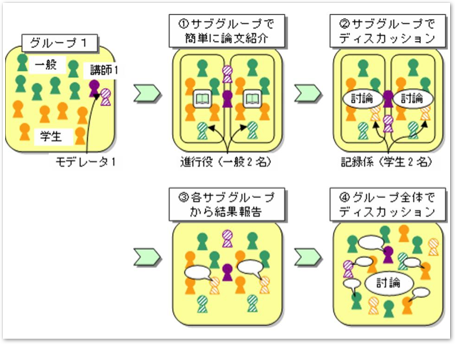
ディスカッションAのプロセス概略図
(3) [2日目午後1]グループディスカッションB
前日のディスカッションAとは異なる講師・モデレータを囲んで,5室パラレルで行います.
ディスカッションBでは,前日のディスカッションAの必読資料ベースではなく,主に【講演内容】に基づいて議論を行います.論文紹介のプロセスはありませんので,代わりに討論時間を長くしてください.特にディスカッションAで出てきたアイデアとの関連も探ります.
※ここでも,必ずしもアイデアを一本化する必要はなく,自由にディスカッションして,3日目の発表会のための材料を見出す作業と位置づけます.
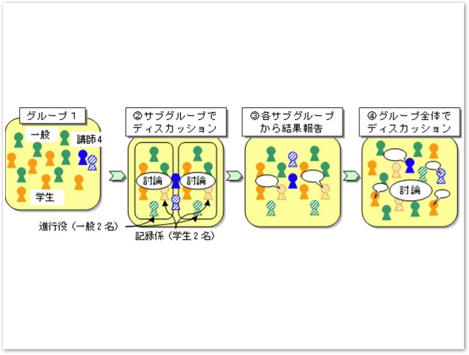
ディスカッションBのプロセス概略図
(4) [2日目午後2&夜]グループディスカッションC(学生メイン)
2つのサブグループ単位で学生が中心となって,3日日の発表会に向けて,より深く議論します.特にディスカッションAとBの内容を相互作用させて新しい研究アイデアを出し合います.
1. サブグループ単位で議論してもらい,発表会の研究アイデアを立てます.
2. 3日目の発表用にパワーポイントなどで発表資料を作成します.
(各自ノートパソコンをご持参ください.)
(各自ノートパソコンをご持参ください.)
※ 3日目の発表時間は質疑応答を含めて10分程度とします.
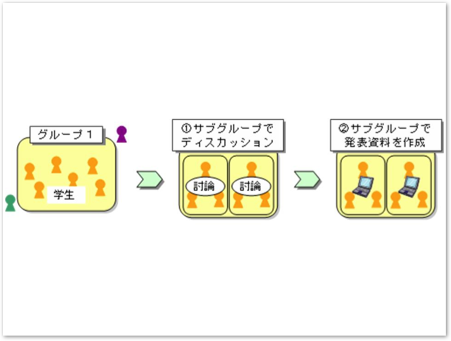
ディスカッションCのプロセス概略図